「HTMLを学んだけれど、実際にWebページを作るときに何から手を付ければいいのかわからない…」
そんな悩みを持つ初心者の方は多いのではないでしょうか。
コーディングは「何となく書き始める」よりも、正しい手順を押さえて進めることで、効率よく、きれいでわかりやすいコードを書くことができます。
この記事では、初心者向けにHTMLコーディングの正しい手順を解説します。
ファイル準備からHTML・CSSの流れ、さらに効率化のコツまでまとめました。
これからコーディングを始める方はぜひ参考にしてください。
HTMLコーディングを始める前に知っておきたいこと
コーディングは「設計」が大切
HTMLコーディングを始めるときにありがちなのが、いきなりコードを書き始めてしまうことです。
しかし、実際のWeb制作では「設計=どんな構成にするか」を事前に考えることが非常に重要です。
- ページの構造がわかりにくくなる
- コードの修正に時間がかかる
- デザインのズレや崩れが増える
といった問題が起きやすくなります。
設計で考えておきたいこと
- ページのレイアウト
ヘッダー、メイン、フッターをどう配置するかを紙やツールでざっくり描いておきましょう。 - 必要な要素の洗い出し
見出し、段落、画像、ボタン、リンクなど、どのような要素が必要かをリスト化します。 - ファイルやフォルダの構成
HTML、CSS、画像フォルダを最初に整理しておくと、作業途中で迷わなくなります。
ワイヤーフレームを作るとスムーズ
設計の段階では「ワイヤーフレーム」を作るのがおすすめです。
ワイヤーフレームとは、Webページのレイアウトをシンプルな枠や箱で表現した設計図のことです。
- ヘッダー(ロゴ・ナビゲーション)
- メイン(見出し・本文・画像)
- サイドバー(必要なら)
- フッター(著作権や問い合わせ先)
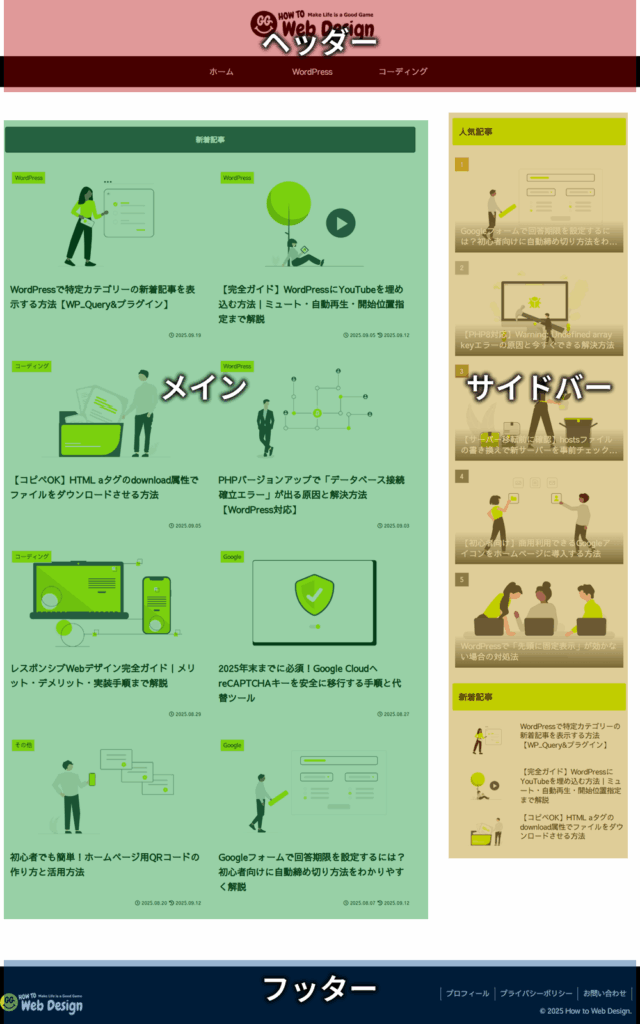
このように大枠を決めてからHTMLを書き始めると、ページ全体の流れが明確になり、無駄な修正を防げます。
慣れてくると、パーツ毎にさらに細かく構成を考えられるようになります。
効率的な流れを意識すると作業が早くなる
Webコーディングは、ただコードを書く作業ではありません。
「効率的な流れ」を意識することで、作業スピードも精度も大きく変わってきます。
コーディングの基本的な流れ
- 設計の確認
ワイヤーフレームやデザインカンプをもとに、ページ構造を頭に入れておきます。 - 骨組みを先に作る
まずはHTMLで大枠(ヘッダー、メイン、フッターなど)を作成。細かい装飾は後回しにすると効率的です。 - スタイルを当てる
CSSでレイアウトを整え、全体の配色やフォントをおおまかに反映していきます。 - 細部の調整
ボタンのホバー、余白、レスポンシブ対応などを最後に調整。
- 1つの見出しを装飾してはプレビュー → また別の要素を装飾 → プレビュー、というように細かい部分から始める
- CSSのルールを順番に考えず書き足していく
- 途中でフォルダ構成を変える
これらは作業の戻りが多く、時間を浪費してしまう原因になります。
- 共通パーツを意識する(ヘッダーやフッターは1回作って使い回す)
- スタイルガイドを決めておく(色やフォントを統一して迷わないようにする)
- レスポンシブ対応は骨組みが完成してから行う
効率的な流れを意識するだけで、作業の無駄が減り、修正にも強いコードになります。
HTMLコーディングの基本手順【全体の流れ】
Webサイトのコーディングは、いきなりコードを書き始めるのではなく、全体の流れを意識することで効率的かつミスの少ない制作ができます。
ここでは、HTMLコーディングを進めるときの基本的な手順を紹介します。
ディレクトリ構成を整える
index.htmlをはじめとしたHTMLファイルcssフォルダ(スタイルシート)imgフォルダ(画像素材)jsフォルダ(必要に応じてスクリプト)
最初にフォルダ構成を整えておくことで、ファイルの管理がしやすくなります。
HTMLの骨組みを作る
HTML5の基本構造を記述します。
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>サイトタイトル</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<header>ヘッダー</header>
<main>メインコンテンツ</main>
<footer>フッター</footer>
</body>
</html>この時点ではまだデザインを反映せず、セマンティックなタグで正しい構造を意識することが重要です。
3. 大枠から要素を配置する
- ヘッダー(ロゴ・ナビゲーション)
- メインコンテンツ(記事、商品一覧など)
- サイドバー(必要な場合)
- フッター(コピーライト、リンクなど)
ページ全体の「箱」を先に作ることで、デザインカンプやワイヤーフレームに沿って整理しやすくなります。
4. コンテンツを流し込む
見出し(<h1>~<h3>)、段落(<p>)、リスト(<ul>、<ol>)、画像(<img>)など、必要な要素をHTMLで配置していきます。
この段階では、装飾はせずに文章と構造だけを完成させることがポイントです。
5. 確認と修正
- HTMLの文法チェック(W3Cバリデーターなどを利用)
- 見出し構造が論理的になっているか確認
- alt属性やリンクの有無など、アクセシビリティの基本を押さえる
ここまで終われば、CSSでのデザイン調整にスムーズに移れます。
CSSコーディングの基本手順【レイアウト~デザイン】
HTMLでサイトの骨組みが完成したら、次はCSSで見た目を整えていきます。
CSSは「デザインを反映するスタイルシート」ですが、いきなり細かい装飾をするのではなく、レイアウトから段階的に仕上げていくのがポイントです。
1. CSSリセット・ベーススタイルを設定する
ブラウザごとに異なる初期スタイルを統一するため、CSSリセット(Normalize.cssや独自のリセット)を適用します。
さらに、以下のような基本設定を行っておくと安心です。
html {
box-sizing: border-box;
font-size: 16px;
}
*, *::before, *::after {
box-sizing: inherit;
}
body {
margin: 0;
font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
}
2. レイアウトを決める(大枠の配置)
まずは全体のレイアウトを整えます。
- ヘッダー、メイン、フッターの配置
- グリッドレイアウトやFlexboxを使った横並び
- サイドバーやコンテンツ幅の指定
header, footer {
background: #f5f5f5;
padding: 20px;
}
main {
display: flex;
gap: 20px;
}
aside {
width: 30%;
}
.article {
width: 70%;
}
3. コンポーネントごとにスタイルを当てる
次に、ボタン・見出し・ナビゲーションなどのパーツを整えていきます。
h1 {
font-size: 2rem;
margin-bottom: 1em;
}
nav ul {
display: flex;
gap: 15px;
list-style: none;
padding: 0;
}
nav a {
text-decoration: none;
color: #555;
}
4. 装飾を追加する(色・余白・背景など)
デザインカンプに合わせて、色やフォント、余白を調整します。余白のルールを統一すると、見た目が整いやすくなります。
.button {
background: #007bff;
color: #fff;
padding: 10px 20px;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
}
5. レスポンシブ対応(メディアクエリ)
最後に、スマートフォンやタブレット向けのスタイルを追加します。
@media (max-width: 768px) {
main {
flex-direction: column;
}
aside, .article {
width: 100%;
}
}
6. 確認と微調整
- デザインがカンプ通りになっているか
- デバイスごとの崩れがないか
- 配色・フォント・余白に違和感がないか
細かい部分をチェックして完成です。
実装の注意点と推奨される方法
コーディングは「見た目を整えれば終わり」ではなく、長期的な運用や保守性も考えて実装することが重要です。
ここでは、HTML・CSSを実装する際に意識すべき注意点とベストプラクティスを紹介します。
1. セマンティックなHTMLを意識する
- 見出しには
<h1>〜<h6>を適切に使う - ナビゲーションには
<nav>、メインコンテンツには<main>など意味のあるタグを選ぶ - SEOやアクセシビリティの面でも有利になる
2. クラス名の付け方を統一する(命名規則)
- 意味がわかりやすいクラス名を付ける
- BEM(Block Element Modifier)を取り入れると管理しやすい
例:
.card__title--large {
font-size: 1.5rem;
}
3. 共通パーツは再利用できるようにする
- ボタンやカードなどは共通クラスを作り、複数ページで使い回す
- コードの重複を減らし、メンテナンスが容易になる
4. レスポンシブは「モバイルファースト」で
- スマホ向けのシンプルなスタイルをベースにし、
画面幅が広がるにつれてPC向けのスタイルを追加する
.button {
padding: 8px 12px;
}
@media (min-width: 768px) {
.button {
padding: 12px 20px;
}
}
5. デザインとコードのズレをなくす工夫
- デザインカンプの余白・フォント・カラーを正確に再現する
- FigmaやXDのデザイン仕様を確認しながらコーディングする
- ブラウザ検証ツールを活用して都度チェック
6. コードの可読性を意識する
- インデントや改行を統一する
- コメントで補足を入れる
- 他の人が見ても理解できるコードを心がける
こうしたコーディングの推奨される方法を守ることで、納品後も修正や機能追加がしやすくなり、結果的にプロジェクト全体の効率化につながります。
効率よくコーディングするためのポイント
- 設計を最初に固める
- デザインカンプやワイヤーフレームを確認して、ページ全体の構造や要素の関係を把握する。
- 「HTMLで何をマークアップするか」を整理しておくことで、後で迷わずコーディングできる。
- HTMLは意味を意識して書く
- 見出しや段落、リストなど、セマンティックに正しいタグを使う。
- 初めは
<div>や<span>で仮に書いても、後で意味づけを行うことが学習にもなる。
- CSSはレイアウトから先に作る
- 幅や高さ、余白などのボックス配置を先に整える。
- 色やフォント、装飾は後回しにすることで作業効率が上がる。
- クラス名・IDの設計を意識する
- BEMなどの命名ルールを使い、再利用可能でわかりやすいコードにする。
- 同じパーツを複数ページで使う場合もスムーズに流用できる。
- 段階的に作業を確認する
- HTMLを書いたらブラウザで確認、CSSでレイアウトを整えたら再確認。
- 小さな単位で確認することで、後での大規模な修正を避けられる。
- コードの整理とコメントを忘れない
- 後で自分や他の人が見ても理解できるようにコメントを残す。
- 無駄なタグや重複スタイルを減らすことで、作業効率が上がる。
- 繰り返し練習して作業フローを身につける
- 初めは時間がかかっても、手順を守って繰り返すことで自然と効率化される。
- 「HTML → CSS → JavaScript」の順番を意識すると、迷いが減りスムーズに作業できる。
まとめ|正しい手順を守ればコーディングはスムーズに
コーディングはただ闇雲にコードを書くのではなく、設計を意識した手順で進めることが重要です。
- HTMLはページの骨組みとしてまず構造を作る
- CSSはレイアウトから装飾へ段階的に整える
- クラス名やIDは再利用を意識して整理する
- 小さな単位で確認しながら進めることで修正を減らす
この手順を守ることで、作業効率が上がるだけでなく、後から修正や追加をする際にも迷わず対応できます。
効率よくコーディングするためのポイントを意識しながら、まずはHTMLの骨組みから着実に進めていきましょう。
正しい手順を守ることが、スムーズで質の高いコーディングへの近道です。
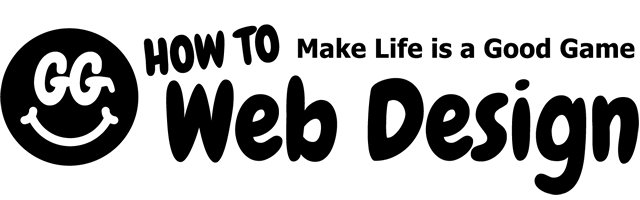


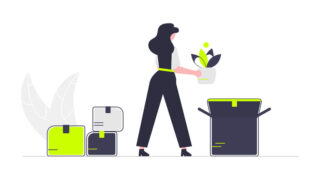
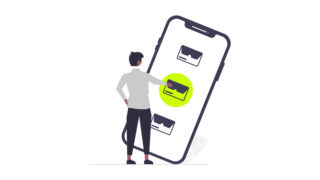


コメント